| |
被扶養者になれる日(認定日)
届出は原則事実の発生日(被保険者の保険加入日、子の出生日など)を認定日としていますが、
届出があまりにも遅れた場合は、この限りではありません。 |
1)親等による要件 |
| |
【同居別居要件】 |
| |
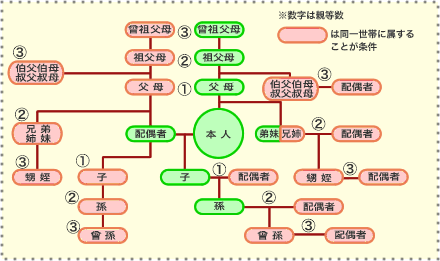
被保険者と同居でも別居でもよい人
★被保険者の配偶者
(事実上の婚姻関係と同様の内縁関係を含む)
★被保険者の子、孫および弟妹
★被保険者の父母、祖父母、曽祖父母 |
被保険者と同居していることが必要な人
★左記以外の 3 親等内の親族
(被保険者の兄姉、伯叔父母、甥姪とその配偶者の父母、連れ子等)
★被保険者の内縁関係にある配偶者の父母と子 |
|
| |
|
| |
2)収入による要件 |
| |
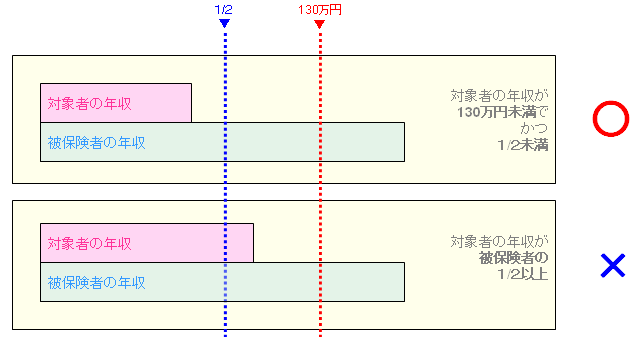 |
| |
【年間収入の定義について】
過去の収入をもとに向こう 1 年間の収入見込みにより判断します。
年間収入が 130 万円未満( 60 歳以上及び障害年金受給者は 180 万円未満) 、
且つ扶養される人の年間収入が 被保険者の
2 分の 1 未満 であることを条件とします。 |
| |
○年間収入の算出方法
※年間収入の対象はすべての収入を対象とし、公的年金、失業給付等も対象とされます。
収入は課税、非課税の別なく含まれます。具体的には、勤労収入、退職金、企業年金、公的年金(老齢年金等)、
労働保険(雇用保険給付金、労災年金、労災一時金等)、社会保険(傷病手当金、出産手当金等)、事業収入(自営業等)、
その他収入。
|
| |
|
| |
【 60 歳以上及び障害年金受給者を扶養に入れる場合】
収入要件のみで判断します。(障害認定者は障害等級に関わらず 180 万円未満であれば認定対象) |
| |
|
| |
【失業給付の受給について】
失業給付は、失業した場合に労働者の生活の安定を図ることを目的としています。
従って、失業給付中ということは、法による生活保障が行われた上で、早く適職を
得て就職する事を目的に支給されているようなものであることから、受給期間中は
健康保険の扶養に入ることができません。
但し、受給額が少額で被保険者によって主として生計を維持しているものと確認
出来た場合は扶養認定します。
|
| |
|
| |
給付日額 × 360 日 = 年間見込収入
例) 60 歳未満:給付日額 3,612 円( 360 日 /130 万円)以上ならば認定対象外
60 歳以上:給付日額 5,000 円( 360 日 /180 万円)以上ならば認定対象外
|
| |
|
| |
また給付日額が上記基準額を超えた場合であっても、待機期間中や受給終了後継続して無職の場合は
受給満了月の翌月 1 日より認定致します。
|
| |
|
| |
【退職金について】
退職(退職した月内)に一括で受け取った場合は、将来に向けての収入がないものとして認定しますが、
退職年金や、企業年金等、退職後分割で受け取る場合については、分割回数・金額を確認し、
基準額を超えた場合は不認定となります。 |
| |
|
| |
【フリーターについて】
基準額を超えた定期的な収入があれば被扶養者になることはできません。
たとえ、アルバイトといえども、会社が一定期間以上継続して雇用する場合は、健康保険や厚生年金などの社会保険に加入することが義務づけられています。
また基準額は 130 万円です。年間 130 万円以上の収入がある場合は自分自身で保険料を負担して医療保険に加入しなくてはなりません。 |
| |
|
| |
【自営業について】
自営業の収入額は確定申告書(税法上)の「所得金額」と判断せず、原則的に「売上額」から「仕入額」を差し引いた額と考えます。
確定申告の「所得金額」は必要経費等の税法上の控除がされており、例えば「修繕費」「減価償却費」等は更なる売上向上を
目指すための先行投資 / 設備投資的な正確を有するものであり、あくまで一時的な支出と捉え「収入額」から控除しないで考えます。
また店舗と住まいが一緒である場合、「家賃」「水道光熱費」「通信費」等の項目が、店舗分と住まい分も含まれているものと判断します。 |
| |
|
| |
※経営状態の悪化等、収入減少が一時的なものであれば扶養追加はできません。
過去数年間の年収から、現在と将来の経営状況を判断・推定する等の調査を行います。
認定条件だけではなく個々の状況にかんがみ、総合的に判断します。 |
| |
|
| |
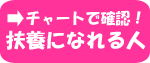 ← こちら! ← こちら! |
| |
|
| |
|